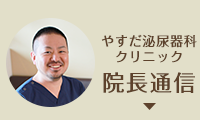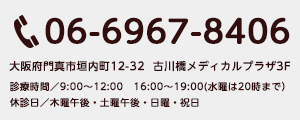~慢性前立腺炎の特徴~
- 2024.04.30
1:怖い病気ではないですが、治りにくく時間がかかり苦労する病気です。 治り方は、基本的に徐々にゆっくりです。半年ぐらいかかる方も多いです。 中々なおらない人もおられます。 患者さんも医師もじっくり診ていくしかありません。 2:原因は不明です。まだはっきりしておりません。 実際に診療をしていますと、きっかけはストレス・疲れ・日頃の生活習慣・長時間座位の状態など をきっかけに発症する方がおおいです。 3:症状は、多岐にわたります。 会陰部といわれるおまたの違和感・痛み、...